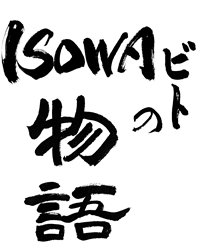|
平成18年2月17日号
第5回 “ISOWAオリジナル”を伝える人たち第1話 “ISOWAオリジナル”を守るためにISOWAを震撼させた、ある“事件”
危機感を強めた経営陣は、ワード社のラインアップに着目。同社は、高速打抜のロータリ・ダイカッタと高速印刷のフレキソ印刷機をひとつにまとめた機種、フレキソダイカッタを販売していたのだ。“段ボール業界の生産合理化要求に応えたい”というISOWAの企業姿勢に、この最新鋭機は見事にマッチしていたといえるだろう。 さっそく、フレキソダイカッタDCF2の生産に着手。しかし、ここで“事件”は起こった。ISOWAのロータリ・ダイカッタが、「特許権を侵害している」と、ライバルの丸松製作所から警告を受けてしまったのだ。 “ISOWA以外のメシを喰ったことがない”という生え抜きで、現製函グループの石川勝紀がこの時を振り返る。 「当時、ISOWAには特許に関する担当者がいなかった。まだ、のどかな時代だったんですね。そこへ突然、警告が届いた。“これは大変だ”ってことで、特許事務所に対応を相談したわけです」 日本で最初にロータリ・ダイカッタを売り出した丸松製作所は、国内における『わん曲ダイ』の特許を昭和42年6月に出願。それが昭和44年2月に認められ、特許の公告時までさかのぼって独占的な製造販売の権利を主張できることになったのだ。 「しかし、よくよく調べてみると、丸松が主張する権利は決して有効なものではありませんでした。無効にできる証拠がいくらでもあった。つまり、丸松の特許を無効にしようと思えば、権利を潰せたわけです」 果たして、ISOWAは争わなかった。丸松の特許を無効にすると、他社も同じ機械の製造販売を始めるのは火を見るより明らか。すると将来的には競合機種が増え、無益な価格競争に巻き込まれてしまう恐れがあったからだ。この“事件”は、話し合いで決着をみた。ロイヤルティ(特許権料)を割り引くことでお互い合意したのだ。 「それでも、ロータリ・ダイカッタがかなり売れたため、相当なロイヤルティを支払うことに。この“事件”は、特許出願の重要性や権利主張を考える上で、大きな契機になったと思います」 “攻め”の権利化で参入障壁を作る
「国によって、発明の進歩性についての権利の判断基準が微妙に違い、それを日本国内で判断するのはすごく難しいんです。字面(じづら)だけじゃ判断できない。間違いを避けるためには、現地に出向き、専門家の判断を求めるのが一番。これは今も昔も変わりませんね」 こう語る石川が、初めて権利獲得のために渡ったのはオランダだった。 「出張先の大阪に現相談役から電話があり“3日後に当社が出願した特許の無効審判があるから行ってきてくれ”と。びっくりしましたよ(笑)。もう30年ほど前、シングルフェーサに関しての権利でした。オランダ特許庁の審判廷で特許の進歩性を認めさせたことにより、その後この特許により、当時の貨幣価値で3億円近いロイヤルティを得て、知的財産の価値を再認識しました」。 他社の権利を侵害しないよう、綿密に調査を進めるのが“守り”なら、参入障壁を作るため、権利化を推進するのが“攻め”だ。 「大企業の権利も中小企業の権利も効力は平等。せっかく社内で開発したアイデア、つまり“ISOWAオリジナル”を積極的に出願し、“攻め”の武器にするのは、業界の中でも早かったと思います」 生産拡大に対応する外注政策
『製品の標準化、部品の規格化を推し進め、安定した品質の少種類の機種を重点的に生産すること。計画的ではない、思いつきの改良では決して良いものはできない』 これとほぼ時を同じくしてISOWAビトのひとりとなったのが、中川弘二(前取締役)だ。専用機メーカーで生産管理に携わってきた経験とタイミングが合致。現会長とともに、立ち上がったばかりの生産管理部門を切り盛りすることになった。 「私の仕事は、ひと言でいえば“受注コントロール”。営業と加工、組立のバランスを取るわけです。どこかでひとつ崩れると全部ダメになる。すごく神経を使いました」 ISOWAが成長した要因のひとつに、協力会社政策がある。昭和30年代の末から自社の工場と協力会社を使い分けはじめ、規模の拡大に伴ってその効果は大きなものとなった。 「協力会社にはできるだけ同じ仕様のものを発注する。品質が安定するし、価格も下がるからです。逆に自社では単発をこなし、ノウハウを蓄えるわけです。いい工場はないかと、あちらこちら探しましたね」 それまで加工に限っていた協力会社政策を、組立の分野にも広げたのが昭和45年。この年、ISOWAはライバルメーカーに対抗すべく、協力会社と同業者の両機能を持つグループを組織化した。それが『ISOWAグループ』である。 文中敬称略 |